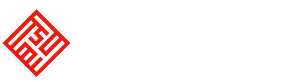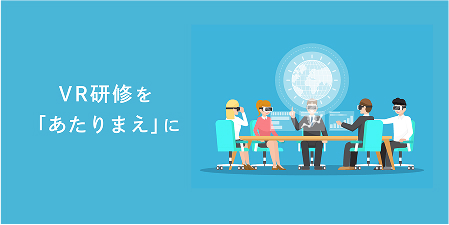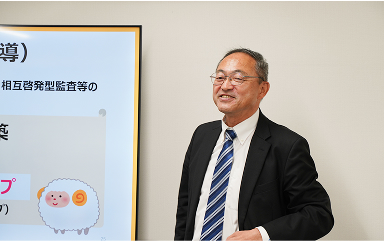「事故の記憶を安全につなげる」
JR東日本の安全教育事例にせまる
2025.05.09錦糸町オフィス

PROFILE

岡本 健太郎 様
東日本旅客鉄道株式会社
建設工事部 基盤戦略ユニット マネージャー

大橋 由貴 様
東日本旅客鉄道株式会社
東京建設プロジェクトマネジメントオフィス 企画戦略ユニット
安全を経営のトッププライオリティと位置づけ、「究極の安全」を目指して企業活動を続けている東日本旅客鉄道株式会社様。
今回はその取り組みの中核を担う、建設工事部の岡本様、大橋様にお話をうかがい、鉄道インフラの現場における安全教育の実態や、デジタル技術を活用した最新の取り組みについてお聞きしました。
東日本旅客鉄道を支える安全の理念
IHIさんが「安全五原則」を定めているように、JR東日本にも安全の心としている「安全綱領」があります。
この綱領は、昭和26年に桜木町で発生した列車火災事故――多くの犠牲者を出した国鉄の重大事故を受けて策定されたものです。当時のGHQからも「鉄道は安全最優先で運営すべきだ」との強い指導があり、その方針が正式に「安全綱領」として定められました。
以来、この綱領は時代の変化や過去の教訓を反映しながら見直され続けています。
たとえば現在の5番目にある「疑わしいときは、あわてず、自ら考えて、最も安全と認められるみちを採らなければならない」という項目は、東日本大震災をきっかけに「あわてず、自ら考えて」の文字が追加されました。震災時、乗務員が避難判断を迫られる場面があり、マニュアルを超えて「その場で最も安全と判断した行動をとる」という姿勢が評価されました。それが明文化された形です。
こうした背景のある「安全綱領」は、いまや列車の乗務員や駅社員だけでなく、工事部門をはじめ全社に共有されており、「安全第一」という意識を組織全体に根づかせる大切な指針となっています。

事故を風化させないためのARについて
積木さんと一緒に取り組んできたことを紹介したいと思います。実は、工事の中でもさまざまな事故がありました。
2014年2月に、京浜東北線が川崎駅で脱線した事故については、ご存じの方も多いかと思います。事故の内容を簡単に説明すると、最終列車が通過する前に、線路上に重機を載せてしまったというものです。
列車がすでに通過したと勘違いして作業を始めた結果、列車と重機が衝撃し、脱線事故が発生しました。このときは回送列車だったため、お客様の死亡事故には至らず、乗務員も軽傷で済みました。しかし、一歩間違えば、前年に起きた福知山線の大事故のような、重大な結果になっていた可能性もあった事故です。
工事というのは、駅舎などが完成すると、工事のために設置した仮設備を撤去し、まるで何もなかったかのようになってしまいます。川崎駅列車脱線事故も、事故が発生した工事用通路は既に撤去されており、現在川崎駅を訪れた今年の新入社員が、そんな事故があったことを知らされなければわかりません。それではいけないという思いから、積木製作さんにご協力いただき、いつ川崎駅を訪れても、あの事故を再現できるARを作りたいと考え、最初に取り組んだのがこのプロジェクトです。
実際にこれは、川崎駅のホームに立って、タブレットを駅舎の方向にかざしている様子です。事故は夜中に発生しました。列車があのスピードで突っ込んできた中に、大きな重機が突然入り込み、衝突して脱線しました。
今ではその痕跡もなく、現場を見ただけではまったく分かりません。しかし、タブレットをかざすことで、その時の状況を目の前に再現できるようになっているので、「この場所で事故が起こった」という事実を風化させないために、事故が発生した2月には、毎年必ず社員が現地に赴き、このARを通じて事故の体験・体感を行っています。

一人じゃないVR体験――270度シアターで“危険”を共有
事故の再現体験はVRでも作成しています。ですが一人ずつしか体験できず、大勢で同時に見ることができないという問題がありました。そこで、現在私たちが所属している東京建設プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)内に270度のシアタールームを新たに設置しました。このシアターで体験者のVR映像を投影することで、複数人が同時に没入感を持って体験できるようにもしております。
他にもVRについては保守用車の使用手続きをVRの中で操作手順を学ぶVRも作成しています。この保守用車は、列車の運行がない夜間などに線路に入って作業を行うための車両で、運用には正確な手続きが求められます。実際に使われているタブレットの操作を、VR空間上で再現していて、体験者はそのインターフェースを使いながら手続きを進めていきます。操作を正しく行えば次に進めますが、ミスがあれば警告音が鳴って間違いをその場で確認できる仕組みです。
さらに、間違った手順を取ると「列車と接触してしまう」といったシミュレーションにもなっており、ただ覚えるのではなく、体験を通じてリスクを実感できるようになっています。
最後にはスコアが表示され、自分がどこで間違えたかを振り返りながら、周囲の参加者と一緒に意見交換する形の実践的な研修になっています。
点群データで進化する現場管理
VRやARとは少し離れますが、点群データを活用したデジタルツインの取り組みも進めています。構造物をスキャンして記録し、寸法の確認や状態の把握、検査などに活用しています。
この取り組みの中で、開発されたのが、TRANCITYというソフトです。そこから弊社出資でスタートアップのCalTa株式会社を立ち上げ、現在は本格的な運用を始めています。
当初は鉄道関連の用途でしたが、今では自治体や工場にも広がっており、工場では点群を使って在庫や空きスペースを可視化し、在庫管理に活用しています。
現在取り組んでいる具体例としては、既存コンクリートに鉄筋を後から差し込む工事において、鉄筋の出代や埋め込み長さを点群で記録・確認する作業があります。
また、土砂崩れなどの災害時にはドローンで点群データを取得し、地滑りの規模を即座に把握して復旧対応に役立てるといった使い方も進めています。これにより、現地調査にかかる時間を大幅に短縮できます。
このように、BIMや点群といった新しい技術の実践活用も進めており、今後もこの分野で積木製作さんと連携を深めていきたいと考えています。

研修の負担軽減と教育の質を両立させるeラーニング
現在は、点群やデジタルツインの取り組みに加えて、eラーニング事業も進めています。
きっかけはコロナ禍。集合研修ができず、講師も退職してしまい、「それならeラーニングにしよう」と社内向けにスタートしたのが始まりでした。
その後、他鉄道会社様から「教育に困っている」との声を受け、第三セクターや地方の民鉄向けに提供を始めたのがeラーニングコンテンツの販売「KeYing」です。
単に動画を配るのではなく、各社の要望に応じたeラーニング教材の制作から受講管理、フィードバック回収まで一括提供。顔認証や“居眠り検知”など、不正防止機能を備えたLMSも導入しています。研修の負担軽減と教育の質を両立できる仕組みとして、全国の民鉄で導入が始まっています。今後は、eラーニングとVRを組み合わせた形も模索中で、復習や定着の面でもさらなる可能性を感じています。
工具置き忘れ防止の実践研修の取り組み
株式会社杉孝 ご担当者:鉄道の安全教育の場で、協力会社さんの研修に参加したことがあります。夜間工事では、限られた時間内で作業を終える必要があり、工具の置き忘れなど、ヒューマンエラーが大きなリスクになります。
これまでのVRは墜落など「ハード系」事故の対策が中心でしたが、判断ミスや注意力の低下といったヒューマンエラーへの対応も進められているのでしょうか?
JR東日本 岡本様:実は、「工具の置き忘れを体験するVR」はすでに作っていまして、現場を歩きながら忘れ物を見つけて指摘する形式になっています。工具の位置は毎回ランダムに変わる仕組みで、年1回ほど研修で活用しています。ただ、少し古くなってきたので、そろそろ更新を検討中です。
その現場に即した臨場感というか没入感を持てる訓練を作れるかというところに注力しており、ただ見るだけの体験ではなく、「実際に歩かないと意味がないだろう」ということで、バラストや砂利の上を歩くような感覚を再現するために、健康マットのようなボコボコしたマットを敷いて、その上を歩かないとVR内を進めないような仕掛けも取り入れたこともあります。