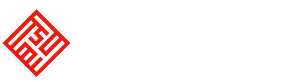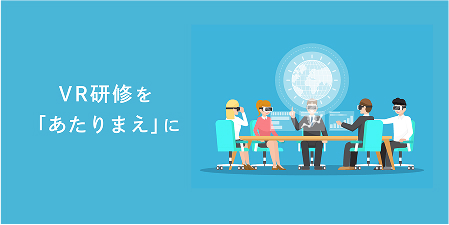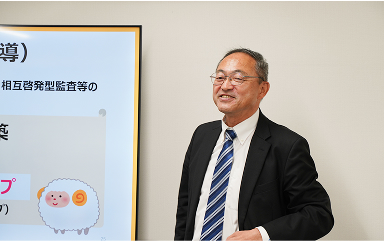足場のプロが実践!現物×メタバースで
進化する安全教育について
2025.05.09錦糸町オフィス

PROFILE

大久保 卓也 様
株式会社杉孝
技術営業部 部長

片野坂 考成 様
株式会社杉孝
技術営業部 足場安全コンサルティング課 課長
1955年の創業以来、仮設機材のレンタル・販売を通じて足場のプロフェッショナルとして、建設現場の安全と効率を支えてきたのが、株式会社杉孝様(以下:SUGIKO)。
『建設現場から労働災害をゼロにすること』のミッションを実現するために顧客への安全教育に取り組まれる中での気づき・ノウハウをSUGIKOの大久保様 片野坂様にお話いただきました。
足場レンタルのSUGIKOがなぜ、安全教育を始めるのか?
足場のレンタル事業を行うSUGIKOがなぜ安全教育の活動を行うのか、現在の取り組みについて片野坂様よりご紹介いただいた──。
創業当初から現場に足場を提供してきたのですが、その現場で災害が発生したことがありました。そうした経験を踏まえて、当時の社長(現在の会長)が『足場を貸し出すだけでなく、その先にある“安全”も提供すべきではないか』と考えたのが、安全教育への取り組みを始めるきっかけとなりました。
私が所属するチームでは、足場の点検や組み立て指導、座学での講演などを実施しています。さらに、安全教習にも取り組んでおり、建設業で必要なライセンスの発行事業の一部をお手伝いさせていただいています。
当社の理念の中には「安全と効率の実現」というものがあります。皆さんの場合、多くは協力会社さんや職員の方、あるいは一緒に働く作業員の方々に対して教育を行うケースが多いのではないかと思います。
一方で、当社はレンタル会社ですので、自らが作業をするわけではありません。つまり、建設工事現場で実際に働いているのはお客様になります。私たちの場合は「お客様に向けて教育を行う」という形になり、その点において社内に向けた安全教育とは少しスタンスが異なると感じております。

安全の原点「足場点検」への取り組みについて
私たちの活動の基盤は、現場での足場点検です。ゼネコンをはじめ多くの現場に伺い、「全層・全スパン」を基本として細かく確認します。くさび式足場(次世代足場)はもちろん、単管足場やわく組足場、吊り足場にも対応しており、幅広い経験があります。
現場では、法令違反や不安全な箇所が見つかることも多く、点検時に指摘しますが、現場の方々にとっては「なぜダメなのか」が分かりにくいケースも少なくありません。いわゆる「KKD」、勘と経験と度胸でやっている、という文化が根強く残っています。そうなると、自分たちが長年やってきた方法のどこが間違っているのか、なかなか理解できないんです。
だからこそ私たちは、「正しい知識を、わかりやすく伝える」ことを大切にしています。再点検で改善が見られるとき、現場が自ら安全を考える力が育っていることを実感できます。
初回点検から2か月後に再訪すると、危険箇所が大きく改善されていることがあります。現場の皆さんが自ら理解し、改善に取り組んでくださった証です。私たちの目標は、「私たちがいなくても、現場が自ら安全を守れる状態」を実現すること。その理想を胸に、日々の活動を続けています。
現物の実演で「危険」を体感させる
私たちは、「見て・聴いて・感じる」ことで危険への感受性を高めていくため、デモンストレーションによる安全教育を実施しています。たとえば、親綱1本に2人の作業者が安全帯のフックが同時にかかった場合、どうなるのか。教科書には「やってはいけない」と書かれていますが、実際に墜落事故が起きたらどうなるのか、現場の皆さんの前でダミー人形を使って再現します。
実演では、足場に人形が接触したときの金属音の衝撃や、墜落時の挙動を実際に目にすることで、危険性をより直感的に理解していただけます。「本当に危ないことなんだ」と、言葉ではなく体感として伝わるのです。
特に、旧来の腰ベルト型安全帯では、荷重が一点に集中するため非常に危険です。過去にはダミー人形の上半身と下半身が分断されるような現象も発生しました。これは私たちにとっても想定外でしたが、逆に「実際に何が起こるのか」をリアルに示すことができたと感じています。
こうした取り組みは、導入当初から現場の皆さまに高く評価されており、「見ることで納得できた」「映像よりも現実の方が説得力がある」といった声も多く寄せられています。現場の安全意識を根本から高める手段として、非常に大きな手応えを感じました。
VR教育を「自分ごと」の体験にするための工夫とは?
また、私たちは一緒に体感し、参加してもらうことを大切にしています。飽きさせない、安全教育にするために重要なのは、「自分ごと」として捉えてもらうことが大事だと考えています。
そんな我々ですが2018年にVRコンテンツの製作を開始しました。私たちは基本的に足場のレンタル会社ですので、わく組足場からの墜落体験や、橋梁工事で仮設される足場からの墜落体験など「足場に特化したコンテンツ」を揃えていっております。
積木製作さんと一緒に制作させていただいたVRコンテンツで「可搬式作業台を使った体感訓練」を紹介します。こちらは決まった行動を取ると事故が起こる1本道のシナリオのVRとは異なり、受講者自身の操作、行動によって結果が変わる「ストーリーの分岐」を採用しています。
研修などでVRを複数人が順番に体験する場合、教育される皆さんは感じていらっしゃると思いますが、
VR教育では、モニターに体験映像を投影することが多いので、最初の人が体験した後の人は「次に何が起こるのか分かってしまう」という課題がありました。
「ストーリーの分岐」がある分岐型VRでは、1人目も10人目も、どんな展開になるか分からないんです。だからこそ、全員が緊張感をもって、真剣に体験できるようになっています。
更にもう一つ私たちのVRの大きな特徴として、よりリアルに、臨場感をもって体感していただくために、実物の足場の上を歩いていただく方式を取り入れています。
実際の足場の上を歩くと、ほんの数ミリですがわずかに沈み込む感覚があるんです。この沈み込みがあることで、仮想空間への没入感が一気に高まり、教育効果も飛躍的に上がると運用する中で実感しています。
三機工業 ご担当者様:もし体験者が例えば1人目が落ちてしまい、次の人は落ちなかった……といった形で、結果がばらついてしまう場合、「正しい作業手順」はどのように伝えているのでしょうか?
SUGIKO 片野坂様:私たち専門スタッフが常に体感者の隣についていますので、その場で直接声をかけてフォローするという形をとっています。
三機工業 ご担当者様:VRの体験中に実際に自分が小さい足場の上に立って歩く体験は安全面でどの様に配慮されているのでしょうか?
SUGIKO 片野坂様:確かにVRを装着した状態で実物をまたいだり歩いたりするのは、確かに危険が伴います。ですので、積木製作さんとも協議のうえ、両脇に2人のスタッフを必ずつけて運用することを原則として、最大限の安全配慮を行いながら運用を進めているという状況です。
MR・メタバースを活用した教育について
2021年にはMR技術を活用し、「屋内で足場点検訓練ができる」コンテンツを制作しました。
これまでとの大きな違いは、複数人が同時に参加し、会話をしながら点検を進められる点です。
「ここはこうじゃない?」「いや、こうかも」と意見を交わしながら進められるため、実践的で効果的な訓練が可能になりました。
さらにMRは、現実の風景も視界に入るため、VRのような“没入しすぎる不安感”が少なく、安心して体験できます。足場全体をミニチュア化し、机の上で点検訓練を行うこともできるため、場所にとらわれず実施できるのも利点です。
こうした制約の少なさは、天候や環境に左右されやすい従来の訓練と比べて大きな進歩です。その中でも特に象徴的なのが、積木製作さんと共同開発した「メタバースによる足場の組み立て訓練」です。
この訓練では、仮想空間にアバターとして入り、最大6人まで同時に足場の組み立てを体験できます。足場作業は災害リスクの高い作業のひとつですが、このシステムを使えば、実際に現場に出る前に、安全な室内でしっかり訓練が行えます。
リリースからまだ1年ほどですが、今後の活用には大きな可能性を感じています。無限とは言いませんが、まだまだ多くの展開の余地があると考えており、引き続き積木製作さんと一緒に活用方法を模索していきたいと思っています。
さて、ここまでが当社の取り組み内容になります。2024年の実績で申し上げますと、足場の点検からメタバース訓練まで含めて、年間で約500件、お客様の現場に訪問して対応させていただきました。
三機工業 ご担当者様:2020年の前からメタバースを導入しようと検討したことがありましたが、メタバースは統率が取りづらいという面はありますよね。
SUGIKO 大久保様:仰っていただいたように、メタバースが難しいと感じる点としては、ストーリーがあらかじめ決まっていないということと、体感者がこちらの想定した行動を取ってくれないということがあります。
たとえば、組み立て時に開口部を作っておいたとしても、そこから実際に墜落するかどうかというと、可能性としてはかなり低いんですよね。ですので、「この開口部から墜落する」というストーリーをもとに教育をするとなると、どうやって体感者をその方向に導いていくかを、メタバース空間でしっかり設計する必要があります。
SUGIKO 片野坂様:メタバースの中で実施する教育の可能性は、ほぼ無限に近いんです。しかし、無限に近いからこそ、しっかりとした教育計画を立案し、受講者を導いていく必要があります。弊社では、講師役となるスタッフを必ず配置し、受講者をコントロールしながら安全教育を実践しています。
そういった意味では、まだまだ“いい意味での課題”、つまり伸びしろが残っているのかな、というふうに思っています。